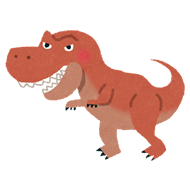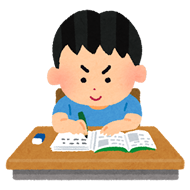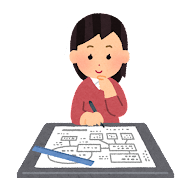季節も夏から秋に移り変わり、読書の秋がやってきました。
先日、ふと思い立って本棚の中からマンガを取り出し読み始めました。
そのとき手に取ったのは「君に届け」という作品です。
主人公は女子高校生で、ありふれた日常の青春と恋愛模様を描いたマンガです。
映画・アニメ・ドラマ化もされているので、知っている人がいるかもしれませんね。
今日は、その中からとてもいいシーンがあったので紹介させてください。
そのシーンは、主人公の友達の『あやね』の進路指導の場面です。
今の自分の成績からみて堅い進路を決めたあやねに対し、担任の荒井先生はこう言います。
「自分の限界をものすごい手前で先に決めてるんじゃないのか?」
あやねは、自分はこの程度だからこれぐらいの学校でいい、と進学先を決めていました。
荒井先生は「レベル下げるのも1つの手だ。悪いことじゃない。」と認めつつ、「選択の幅を自分自身で狭めていないか」と語りかけます。
これをきっかけにあやねは一歩を踏み出します。
受験を控えているみなさんの中に、同じような気持ちで受験先を決めようとしている人はいませんか?
自分の中で無理そうだからとあきらめてしまったところはありませんか。
本当にその学校に行きたいですか?少しだけ自分と対話してみるのはどうでしょうか。
自分と向き合い全力で取り組んでいるからこそ見えるものが、きっとあると思います。
自分の進む方向が決まったら、あとは全力で自分のできることをやっていくだけです。
限界を自分で決めないように少しずつ出来ることを増やしていけば、限界だと思っていたところはいつの間にか限界ではなくなっていると思います。
そういう積み重ねが自信につながっていきます。
春夏と季節は過ぎていきました。
残りは秋と冬。
この季節を乗り越えて満開の桜が咲く中で笑顔を満開に咲かせる春にするために、がんばっていきましょう。