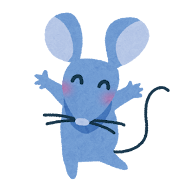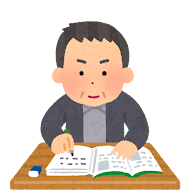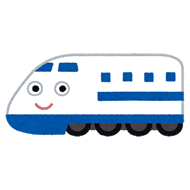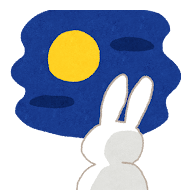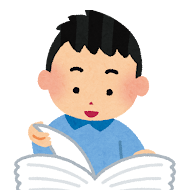みなさんは「箱根駅伝」を知っていますか?
毎年1月2日と3日に開催される関東の大学駅伝で、お正月の風物詩にもなっています。
東京から神奈川県の箱根・芦ノ湖間を、往路5区間(107.5Km)と復路5区間(109.6Km)、合計10区間(217.1Km)で競われます。これは学生駅伝では最も長い距離です。
箱根駅伝に出場できるのは関東圏の大学で、「前年度の上位10校」と「予選会を通過した10校」、それに「関東学生連合チーム」を加えた21チームです。
箱根駅伝には、11位以下になってしまうと、次年度は予選会から参加しなければならないというルールがあります。
そして、その予選会で10位以内に入らなければ、箱根駅伝には出場できません。
予選会は毎年10月に行われ、40校近くが出場枠を争います。
予選会では、各大学の10~12人がハーフマラソンのコースを一斉に走り、各大学の上位10人のタイムを合計して順位を競います。
10人の合計タイムで決まるため、走り終わっても予選を通過できたかどうかはすぐにはわかりません。
今年の予選会は、雨上がりの蒸し暑さに加え、容赦ない強い日差しがふり注く過去最悪のコンディションで、波乱が続出しました。
フラフラで今にも倒れそうなランナーたちをテレビで観ていて、何度も声が出そうになりました。
予選会が終わり、いよいよ運命の結果発表の時・・・。
発表は「結果発表ボード」に、第1位の大学から読み上げ・開示されていきます。
「第1位 立教大学 記録10時間52分36秒」
次々と箱根の切符を勝ち取った大学が呼ばれ、そのたびに大きな歓声が上がります。
9位まで呼ばれて、箱根駅伝に出場できるのはあと1校だけ。
「第10位 順天堂大学 記録11時間1分25秒」
その瞬間、順天堂大学の選手たちは抱き合って喜びを爆発させました。私も感動で鳥肌がたちました。
その後、第11位が読み上げられました。
「第11位 東京農業大学 記録11時間1分26秒」
10位と11位のタイム差は、なんとわずか1秒。
東京農業大学の選手たちは泣き崩れました。
たった1秒。しかし、それはとてつもなく大きな1秒でした。
勉強にも同じことが言えると思います。
1点でも多く!1問でも多く!これを生み出すことは決して簡単なことでないですよね。
しかし、日々の積み重ねによって叶えられると私は信じています。
だからといって、毎日全力でガツガツ頑張り続けるのは難しいでしょう。
小さくてもいいんです。
積み上げていってください。
今日の積み上げが「0.001点」「0.001問」でも構いません。
未来の1点・1問に必ずつながっていきます。