
世の中大変な状況です。新型コロナウィルスの感染拡大を受けて、外出自粛の3密、①密閉空間(換気の悪い密閉空間)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる))の回避・休校期間…。
様々な影響が出てきていますが、それとは関係なく季節は移っていきます。春の陽気が日に日に勢力を増して、日差しの強い日には夏を予感させる暖かさが顔を出し始めました。それに伴い、いろいろな生物も活動を始めています。
『昆虫』もそんな生物の代表でしょうか。チョウが春の花に集まり、バッタが卵から孵化(ふか)して草にとまっている、そんな姿を目にするようになりました。もう少しすれば夏の昆虫が活動し始めます。カブトムシはその準備としてそろそろ蛹(さなぎ)になる頃でしょうか。今回はそんなカブトムシ同様、夏の昆虫の代表、『蝉(セミ)』について話をします。
セミがどんな一生を過ごしているかは知っている人が多いと思います。幼虫の期間は種類によって異なりますが、短い種類でも3年。大きくて力強いイメージ(先生だけ?)のクマゼミは5~6年間土の中で過ごします。そんな長い期間土の中で過ごしてやっと地上に出てくるのですから、あんなに一生懸命鳴くのもわかりますよね。(そんな成虫の期間は約1か月…短いですね)それだけ長い時間をかけて成虫になるセミですが、種類によってはもっと長く幼虫として地中で過ごすセミもいます。『17年ゼミ』と言われる種類で、名前の通り17年間も地中にいます。なぜそれだけ長いのか…。
歴史をさかのぼれば『氷河期』と呼ばれる時代の環境が影響しているそうです。地上に出てきても低い気温ですぐに死んでしまうため、なるべく長い時間地中にいようと、幼虫でいられる限界の期間まで地中にいたことが原因とのこと。
では、地上に出てきてもすぐ死んでしまうのなら、その時に何をするのか。それは「子孫を残す」です。地上に出てきてすぐにオスはメスを、メスはオスを探し子孫を残すそうです。ただ不思議なのは、この17年ゼミ、きっちり『17年間』地中にいて、17年ごとに一斉に成虫になるそうです。(地域によって『13年ゼミ』のところもあるそうです。その規模はすさまじく「北米でセミが大発生!! 数十億匹の大合唱で電話の声も聞こえない!!」などとニュースになるほど。
なんでそんなにきっちり17年で成虫になるのか、少しずれて16年や18年になってもおかしくないだろうに…と思うのですが、それには大きな理由があります。
長い期間地中にいることになった原因の一つである『氷河期』では、成虫になるタイミングが一匹ずつ異なればどうなるか。せっかく地上に出てきてもオスとメスが出会えないかもしれません。そうなれば子孫を残すことができずに、最終的には絶滅していくしかありません。気候が安定してきた現代でも、それは同じ事です。外敵から身を守る手段をあまり持たないセミとしては、「自分の身に何があったとしても種族(同じ種類のセミ)の繁栄があれば良い」として、鳥に食べられようが、蛇に食べられようが、子供に取られようが…それでもかまわないくらいの大群で成虫になる方が、子孫を残せる可能性が高いのです。そうやって残された子孫はさらに決意するわけです。『17年後に成虫になって会おう!』
すごいですね。17年という『期限』をおおきな目標として過ごします。命がけです。
このセミの『期限』という名の『目標』はぜひ見習いたいものです。命がけ…とまではいかないかもしれませんが、君たちにも譲れない「期限」があるはずです。受験生は当然「受験日」が期限となるでしょう。もっと先の「将来の目標」に期限を合わせるなら「社会人になるまで」が期限でしょうか?
セミ同様、私たちも限りある命を生きる限り、一度きりの人生だからこそ期限からは逃げられません。先生もまだまだこれからです。どうせ生きるなら未来の自分をもっと大切に大きな夢を描きたいです…そういう意味では、君たちの可能性は無限大ですね。
今からならなんにでもなれます。ただし、その実現のためには「期限をどこに設定するか」「目標をどの高さまでもっていけるのか」思い込みを外して、勇気をもって目標を持つことが大切になると思います。
今はしっかりと自分を見つめなおす時間、将来に思いをはせる時間が取れるはずです。これを良い機会だと捉えて、ぜひ考えてみてください。
(ちなみに12年や18年ではなく、『13年』や『17年』になったのも理由があるようです。ヒント『素数』。この謎を解き明かしたのは日本の昆虫学者だそうです。興味のある人は調べてみよう。)





 お家の庭や学校の校庭の隅に必ずいる、指でつっつくとクルンと体を丸くする…そうダンゴムシ!
お家の庭や学校の校庭の隅に必ずいる、指でつっつくとクルンと体を丸くする…そうダンゴムシ! 1月から、2020年のNHK大河ドラマが始まっています。タイトルは「麒麟がくる」。物語の主人公は戦国時代の武将・明智光秀ですが、彼がアフリカから首の長いキリンを連れてくるというストーリーではありません。そもそも、あまり聞きなれない“麒麟”ですが、確かに、どんな動物図鑑にも載っていません。それもそのはず、その不思議な生き物は、鳳凰・龍などと同様の、古代中国の神話に出てくる伝説上の霊獣なのです。
1月から、2020年のNHK大河ドラマが始まっています。タイトルは「麒麟がくる」。物語の主人公は戦国時代の武将・明智光秀ですが、彼がアフリカから首の長いキリンを連れてくるというストーリーではありません。そもそも、あまり聞きなれない“麒麟”ですが、確かに、どんな動物図鑑にも載っていません。それもそのはず、その不思議な生き物は、鳳凰・龍などと同様の、古代中国の神話に出てくる伝説上の霊獣なのです。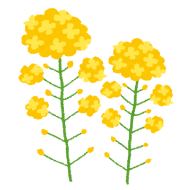 3月になり、庭先を見ると、硬い冬の地面を押し上げ、植物たちがむくむくと春に向かって成長していく気配を感じとることができます。
3月になり、庭先を見ると、硬い冬の地面を押し上げ、植物たちがむくむくと春に向かって成長していく気配を感じとることができます。 新型コロナウイルス感染症の影響で学校が休校になり、1週間が過ぎましたが、皆さんはどのように過ごしていますか。
新型コロナウイルス感染症の影響で学校が休校になり、1週間が過ぎましたが、皆さんはどのように過ごしていますか。 前回の朝礼では新型コロナウイルス感染症への注意事項などをお伝えしましたが、先週、政府から全国へ学校休校の要請が出されてことを受けて、能開の教室も休校することになりました。(一部地域を除きます)
前回の朝礼では新型コロナウイルス感染症への注意事項などをお伝えしましたが、先週、政府から全国へ学校休校の要請が出されてことを受けて、能開の教室も休校することになりました。(一部地域を除きます) 今、日本でも新型コロナウイルス感染症が広がりつつあり、テレビや新聞で毎日のように報道されていることは、皆さんも知っていると思います。
今、日本でも新型コロナウイルス感染症が広がりつつあり、テレビや新聞で毎日のように報道されていることは、皆さんも知っていると思います。