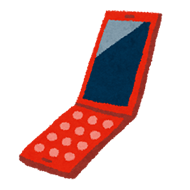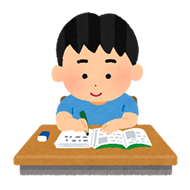今日10月19日は、アメリカ海軍の提督、アーレイ・バーク海軍大将の誕生日です。アーレイ・バークは太平洋戦争時に大きな戦果を挙げる活躍をしました。「31ノット・バーク」という異名を得たことでも知られています。
さて、このバーク提督、日本に来る前は大の嫌日家として知られており、公式の場で日本のことを大嫌いだと公言することもたびたびありました。しかし、ある出会いをきっかけにして大の親日家に変わります。
GHQの高官として帝国ホテルに寝泊まりしたのですが、最初、日本人ボーイが荷物を持とうとすると、「触るな。おれに一切かかわるな。」とののしったくらいです。ある日、殺風景な自分の部屋に、多少なりともうるおいを与えようと、店で買ってきた花を一輪、コップにさしておいたことがありました。
夜、帰ると、それが小さな花瓶にさしてあったのです。バークは激怒し、すぐフロントに降りて行って、「勝手なことをするな。」と怒鳴り込みました。しかし、帝国ホテル側は、なにも指示を出していない、と言うばかり。
やがて、花瓶には、新しい花がさしてあるようになりました。またこれで怒ったバークは、ホテルに激しく抗議しました。「誰が、こんなことをしているのか、犯人を探し出せ」結局、それはバークの部屋を担当していた帝国ホテルの女性従業員であることが判明したのです。バークはこの日本人女性を呼び出し、厳しく問いただします。
「なぜ、こんな余計なことをした?」
「花がお好きだと思いましたので。」
彼女は、自分のわずかな給料から、ときどき花を買っては、バークの部屋に活けていたことがわかったのです。
バークは、一応納得し、それではその対価を自分は払わなければならないといって、金を押し付けました。しかし、彼女は頑として受け取らなかったのです。彼女いわく、宿泊客に、気持ちよく過ごしてもらいたいというだけのことだからお金はいらない、と。バークには、これがまったく理解できませんでした。いわゆるアメリカのチップという習慣くらいにしか理解できなかったのです。さらにバークは、彼女の身の上を聴いて驚きます。
彼女は戦争未亡人だったのである。夫は海軍の駆逐艦の艦長で、アークも参加した戦闘で戦死していました。バークは、さすがに心が揺れ、「それは申し訳ないことをした。わたしがご主人を殺したのかもしれない。」
しかしその女性は、はっきり言ったそうです。「あなたがなにもしなかったら、夫があなたを殺していたかもしれません。誰が悪いのでもありません。」バークは、深く考えさせられてしまいました。「自分が、心の底から日本人を憎んでいる一方で、この女性はその立場を超えて、自分をもてなしている。この違いは、一体何なのか?」
のちに、バークは述べています。「彼女の行動から、わたしは日本人の心意気と礼儀というものを知った。日本人の心には、自分の立場から離れ、公平に物事を見ることができる資質があるのだ。」この帝国ホテル滞在中、バークはさまざまな、日本人のその心意気に圧倒されていくことになりましたが、それはまた別の話。
いくつもの逸話を経て、バークは次第に日本人への憎しみが消えていき、むしろ、敬愛の念を抱き始めていったのです。バークは、一刻も早く米軍による日本の占領を解き、独立を回復させるよう、GHQとアメリカ政府に訴えたのです。
朝鮮戦争がはじまると日本海軍の再建も説き、1954年に海上自衛隊が設立されることになります。1961年、彼は海上自衛隊創設に力を尽くした功績で、日本から勲一等旭日大綬章(日本でもっとも価値の高い勲章)を贈られました。
1991年、バークは96歳で亡くなりました。各国から数多くの勲章を授与された人物でしたが、葬儀のときに、彼の胸につけられたのは日本の旭日大綬章ただ一つだけだったそうです。それは、バークの遺言だったのです。そのため、ワシントンの海軍博物館にあるバーク大将の展示コーナーには、日本からの勲章だけ、一つ抜けたままになっています。彼にとって、他のどの勲章より、日本で天皇から下賜された旭日大綬章が生涯の栄誉と思っていたようです。
先生は、このお話を最初に聞いた時、「相手を思いやる気持ち」がかたくなな心を溶かすことがあるのだな、と思いました。帝国ホテルの女性のように、ちょっとした心遣いを大事にしたいですね。