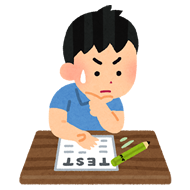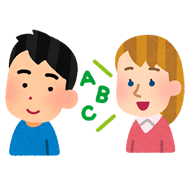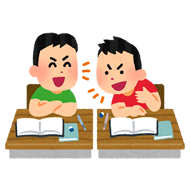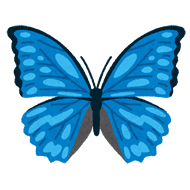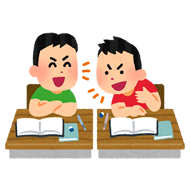
あるとき、ある友人と話をしていて「へぇ~」と思ったことがありました。
友人:1から10まで言ってみて
先生:いち、に、さん、し、ご、ろく、しち、はち、きゅう、じゅう
友人:じゃ、次は10から1まで言ってみて
先生:じゅう、きゅう、はち、なな、ろく、ご、よん、さん、に、いち
友人:何かに気づいた?
先生:この年齢になって大声で数を数えるのは恥ずかしいってことに気づいた
友人:いや、そうじゃなくて、‘し’が‘よん’で‘しち’が‘なな’に。。。
先生:え。。。? あ、ホントだ!
友人:これ、ほとんどの人がそうなんだよね(ニヤリ)
どうせ自分の発見ではなく、誰かから聞いたネタのくせにやたらと得意気なその友人の態度に苛立ちながらも、心の中では「俺は半世紀もの間、これに気づかず生きてきたのか!」という衝撃と動揺がしばらく渦巻いていました。
そして今度は自分が誰かにこれを仕掛けてみたくなり、次の日に職場で同僚に試してみました。しかし、その同僚はこのネタを知っていたようで、「いち、に、さん、よんっ、ご、ろく、ななっ、はち、きゅう、じゅう」と‘よん’と‘なな’を強めに言い、おまけにニヤリと笑って返したのです。その瞬間、普段は使わないように心がけ、生徒たちにも禁じている言葉が思わず口から出てしまいました。
「ウザっ!」
そりゃ、この場面にこれ以上に相応しい言葉はないし使いたくもなるわ。「ウザい」って言葉、侮れない。この言葉を使いたがるキミたちに強く心から共感できたので、その瞬間の先生の何とも言えない感情にもぜひ共感してほしいものです。
さて、この「うざい」という言葉は「うざったい」という、今はほぼ全ての国語辞典にも載っている言葉から派生しているようです。そして、その「うざったい」も元々はある地域の方言だったものが、いつしか全国区になったということのようです。「うざい」も、将来どの辞書でも見られるようになるかもしれませんね。
言葉はいろいろ調べてみるととっても興味深いものです。例えば、最近よく聞く「ウイルス」や「ワクチン」という言葉。英語で「ウイルス」は [ virus ]、「ワクチン」は [ vaccine ] です。どちらも [ v ] で始まり、あえてカタカナなら「ヴァイラス」「ヴァクスィーン」。これらがなぜ、にごりもしないア行とワ行の発音になってカタカナ語として定着したのでしょうか。英語を専攻して学んでいた学生の頃から非常に不思議でしたが、よく調べてみると語源であるラテン語で [ v ] を使うと「ワ・ウィ・ウゥ・ウェ・ウォ」のような発音をすると最近知ることになり、ようやく四半世紀に渡る疑問が解けたのです。
最近は言い訳や何かができない理由として「コロナだから」「コロナ禍なので」などをまるで流行語のようによく耳にしますが、そんな言葉で簡単に片付けたり、ネガティヴになってただやられっ放しになることなく、今回の [ virus ] [ vaccine ] のように「コロナがきっかけで」知識を得ることだってできるのだとポジティヴにやり返す強い気持ちも持つべきですね。
キミたちにも強い気持ちで前を向き、折れることなく様々なことを吸収して成長していってほしいと強く願い、ずっと応援しています。言葉は変わっていっても、気持ちは変わることなく。