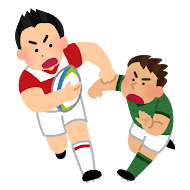

皆さんは「人のまねをすること」についてどう思いますか?
約2年前、先生が暮らしている長崎の中心部にサンドウィッチ屋さんがオープンしました。
そこはアメリカ発祥のファストフード店で、先生がアメリカ留学時代に友人に連れて行かれたお店で、懐かしい反面、苦い思い出のあるお店です。
学生時代に初めてそのサンドウィッチ屋さんに入ったときの思い出話をちょっとお話ししたいと思います。
数種類のパンの中から好きなものを選び、トーストするのかそのままなのか?そして数あるトッピングの中から好みの肉・チーズ・野菜・ソースを順に選んで自分好みのサンドウィッチに仕上げていく形式のお店でした。
自分好みのサイズ・中身に仕上げることのできる大変魅力的なお店でしたが、今まで経験したことのない注文方法で英語でどのように伝えれば良いのかわからず中々注文の列に並べませんでした。
チーズだけでも4~5種類あり、他の具材との相性が分からないため、何を選ぶべきかすら分からない。
さらには、教科書には載っていないフレーズが飛び交う店内。
「自分好みにしよう!」という考えは捨て、『前の人にならえ』で注文し始めました。
目の前に並んでいた巨大な男性が店員さんと交わす会話を聞き、全く同じ言葉を真似しながら注文していきました。
思い出すだけでも緊張感がよみがえってきます。
最後にできあがった、超巨大なサンドウィッチ。
昼だけでは食べきれずその日の夜ご飯にもなりました。
自分好みのサンドウィッチは手に入りませんでしたが、それ以来、同じような形式のお店に入ることが楽しみになりました。
先生はこの経験を通して「観察する⇒真似る⇒進化させる」というサイクルを学びました。
人は誰でも初めて何かをやり始めたり、経験したことが無いことに出くわした時、どうしていいのかわからないで悩むことがあると思います。
皆さんも初めて能開に入ったときに勉強の仕方が分からず悩んだ経験はありませんか?
うまくやっている人や熟練者の動きを観察したりアドバイスをもらいながら、まずは「真似する」ところから始めるとうまくいくこともあると思います。
何事においても、自己流を貫くだけではなく、周りを観察し自分に足りないものを吸収しながら、さらに自分に磨きをかけていけるといいですね。
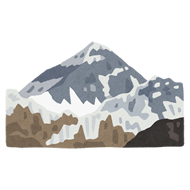


新年になると、何か新しいことをしたいな!と思うのですがみなさんはどうでしょうか?
先生は昨年から言語学に興味を持ち、時間があるときに気になることを調べています。
その中で一番好奇心がそそられたのは、幼い子どもの言語発達についてです。
突然ですが、みなさんは幼い子から「今日、とらのこが降るからはやく帰ろうよ。」と言われたらどう思いますか?
「とらのこって何だ?」ときっと大困惑することでしょう。
実はこれ、「今日は雹(ひょう)が降るからはやく帰ろうよ。」と言いたかったのです。
天気予報で「ひょうがふる」と聞き、ひょうと言えば動物、豹ってなにか虎と似ていたな、じゃあ虎の子だ!と考えたという成り行きでした。
とっても可愛い間違いですよね…。
「そんな勘違いありえないよ!」と笑っている人もいるかもしれませんが、おそらく幼いころに似たようなことを言っているはずですから、ぜひお家の人に聞いてみてくださいね。
さて、言葉というのは年齢を重ねていくにつれ、正しく使える数が増えていくものだと思います。
それではなぜみなさんは言葉が正しく使えるようになっていくのでしょう?
それは、わたしたち人間が訂正・修正を繰り返して学ぶことができるからだと思います。
かく言う先生も、言葉はどう使うのかといったことを語っていますが、幼い頃はとうもろこしを「とうもころし」と物騒な言い間違いをしていましたし、今でも自分の使っていた言葉の誤りに気付くこともあります。
(「準備万端」と「準備万全」って違うんだ!とか)
ただ、少しずつ心身が発達してくると、間違いが「恥ずかしいこと」「してはいけないこと」のような気がしてしまい、なかったことにしたり、放置したり、何か他のせいにしてしまったりしてしまいたくなります。
そこで、間違いを訂正していくことが成長に繋がることを心に留めていてほしいのです。
もちろん、いくら頭では理解していても実行することは生半可な気持ちでは難しいです。
しかし、その大変さ、面倒さを超えた先にある理解したときの気持ちよさを味わってほしい、学びの原動力としてほしい、そして、そのサポートができたら幸せだなと思っています。
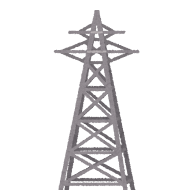
秋は過ぎ去り、冬が本番を迎えつつある昼下がり。
いい加減運動せねばと思い、近所を散歩する。
いい天気だ。雲ひとつない。
遠くに見える真っ青な空と深い緑の山の境界線が好きだ。
たどり着ける訳もないのにそこへ向かって歩みを進める。
ふと、空と山の境界線に白い鉄塔があるのに気づく。
そう言えば、あの鉄塔はどうやって建てたのだろう。
トラックが通るような道があるようには思えない。
まさか人の力で運んでいるのだろうか?
それに鉄塔と鉄塔の間を結ぶ電線はどうやって張ったのか?
次々に浮かぶ疑問と一緒に散歩を続ける。
ふと、目の前に「〇〇の宿跡」と彫られた石碑が現れる。
宿?
ここには昔宿があったのか?
温泉か?温泉があったのか?
温泉に行きたいな。
寒くなってきたな。
帰ってお風呂に入ろう。
湯船につかりながら先ほどの疑問を思い出す。
なぜ?どうして?どうやって?
だめだ、お風呂になんて入っている場合じゃない!
どうやって山の上の鉄塔を立てるのか?
建設場所まで行くための道路を作って資材を運んだり、ヘリコプターを使ったりして運ぶ。
送電線もヘリコプターと地上の作業員との協力で張る。
資材の材質や塗装の色、作業方法の一つ一つに工夫がしてある。すごい。
「〇〇の宿跡」とはいったい何?
昔の街道沿いにあった休憩のための宿。場所によっては峠を越えるための準備をする場所。
街道で有名なのは五街道「東海道」「中山道」「甲州街道」「奥州街道」「日光街道」。
街道は人や物資が行き来するために整備された道のこと。五街道は参勤交代にも用いられた。
街道は日本各地にあり、中でも長崎街道は別名「シュガーロード」とも呼ばれる。
出島を通じた貿易で当時貴重だった砂糖が大量に長崎にもたらされ、街道を通って長崎から佐賀を通り、福岡まで砂糖が運搬された。
このとき街道沿いに砂糖や砂糖を使った菓子作りの技法が伝わり、カステラや丸ぼうろなどの有名なお菓子が生まれた。なるほど。
普段気にも留めない目の前の光景にも、必ず意味や歴史が存在する。
誰かが言った。
「知識を増やすことは、世界の解像度を高めること」
知れば知るほど世界はより鮮明に、より深く、より広がっていく。
知るためのスタートラインは疑問を持つこと。
なぜ?どうして?と感じることが、あなたの世界を広げるきっかけとなる。
今年も残りわずか。
来年もあなたにとって世界が広がる1年となりますように!
そう願いながらこの文章を打つ手が止まる。
キーボードの配列はなぜこうなっているのか?
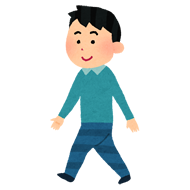


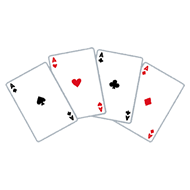
今年もあと1ヶ月あまりとなりました。
能開の教室は北から南までありますので、まだ寒くない地域、雪景色になっている地域など様々かと思います。
さて、みなさんは宇宙の年齢を知っていますか?
宇宙の年齢は様々な観測データを組み合わせて出された結果、138億年といわれています。
人間の一生が仮に100年としてもその年月は途方もないような時間に感じます。
ところで、どこの家にも一つはあるであろう「トランプ」(アメリカの新大統領でありません)は、52枚から成ります(ジョーカーを除く)。
この52枚のトランプの並び方のパターン数と、宇宙が誕生してから経過した秒数では、どちらの数が多いと思いますか?
答えは、圧倒的にトランプの並び方のパターン数の方が多いです。
まず、トランプ52枚の並び方のパターンは、52×51×50×・・・・×2×1となります。
実際に計算するのはやめましょう。
これは計算すると68ケタの数となります。
片や宇宙の年齢を秒に換算すると138億年×365日×24時間×60分×60秒=435196800000000000秒で18ケタとなり、68ケタの数 対 18ケタの数で、トランプの方が圧倒的に多いことになります。
身近に宇宙にも勝る数値が潜んでいるのは考えると不思議でワクワクしますね!
勉強の合間にゲームやYoutubeもいいですが、ちょっと興味のある本を開いてみるのも新たな発見があっていいかもしれませんよ。

