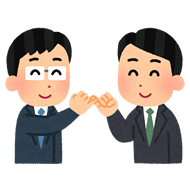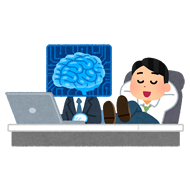今年の夏も35度以上の猛暑日が続きましたが、お盆には一転して天気が不安定になり、各地で大量の雨をもたらしました。
天気というのは私たちの周りにある自然の中で、とても身近なものですね。
空に浮かぶ大きな入道雲を見上げたり、飛行機の窓から雲海を見たりして、あの中に入ってみたいなぁとか、不思議な気持ちになった人もいるかと思います。
雲というのは遠い空の現象と思われますが、たとえば地上で立ち込める霧は地表に張り付いた雲の一種ですし、実はお風呂の湯気もみそ汁の湯気も、暖められた水蒸気が立ちのぼる状態であり、ある意味で雲と同じ現象だと言えます。
気象庁気象研究所の研究官で、雲研究者の荒木健太郎さんの著作「すごすぎる天気の図鑑」では、雲や天気についての解説を、写真やイラストなどで楽しく読むことができます。
荒木さんはアニメ映画「天気の子」を監修されるだけでなく、作品の中にも本人役として登場するそうです。「すごすぎる天気の図鑑」からいくつかの解説を紹介しましょう。
雨のつぶの形はよくあるイメージと違って、頭はとがっていない。
地震雲は地震の前兆ではない、飛行機雲を違う角度からみたもの。
虹は半円ではなく本当は丸いが、虹のふもとまで行くことはできない。
1時間に100ミリの雨は、1平方メートルに100キログラムの水がたまる凄さ。
台風の予報円は台風の大きさではない、確率70パーセントの範囲のこと。
今まで何となく見ていた空や雨や台風のことも、ひとつひとつに科学的な原因がありますが、すべてが解明されたわけではありません。皆さんも目の前にある雲がどんな形で、どこから来たか、考えてみませんか。空を見上げるのが楽しくなりますし、夏休みの自由研究にも役立つかもしれませんよ。