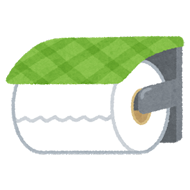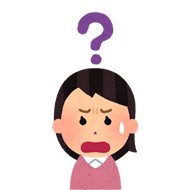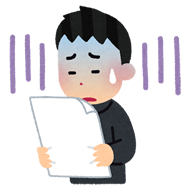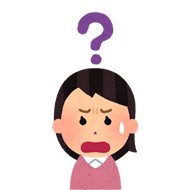
突然ですが問題です!
方位磁石のN極はどの方角を指すでしょう? (小学3年生の理科)
どうでしょうか?皆さん、もちろん分かりますよね。
実はこの問題、アニメ『ちびまる子ちゃん~おねえちゃんついにまる子にあいそをつかすの巻~』にでてきたものでした。
まるちゃんがお姉ちゃんに怒られつつ頑張って勉強をするのですが、珍解答がたくさんでてきます。
例えば社会の選択問題
問題:商店街の人は何をするのか?
まる子の答え:木を植える(だって商店街の佐々木のじいさんは木を植えているから)
問題:海が近くにある村で盛んな仕事は何?
まる子の答え:商業(だって貿易の船が港に着いたらそれを売るじゃん。観光客がたくさん来るところかもしれないじゃん。)
「それは違う!」と言うお姉ちゃんに対して、まるちゃんはこんな風にへりくつを返しながら解いていきます。
さあ、では冒頭の問題にはどんな答えを出したのでしょう。
まるちゃんの答えは、西。
気になるその理由は・・・アルファベットで書くと「西」は「にし」で「Nishi」になるから。
「あ!!Nから始まる!!」ということです。
もちろんどれもこれも不正解なのですが、あてずっぽうではなく、まるちゃんなりに考えた理由で答えているのが面白いなと思いました。「西」をローマ字表記に直すという発想までいったら、あと少しだったのに・・・。英語で北=Northを覚えていたら分かった問題でしたね。
無茶苦茶な答えに笑いつつ、分からない問題に対して空欄で終わらずに、自分の知っている知識からいろいろ考えて答えを出すという姿勢は素晴らしいなぁと思いました。
さて、皆さんは分からない問題に出会ったときどうしているでしょうか。
もちろん調べたり聞いたりして解決してほしいのですが、まずは自分の中にある知識を使って考えてみましょう。
「似たような問題を解いたことなかったかな。」とか「この単元で覚えていることから推測して・・・。」など頭の中を大捜索して考えることで「問題を解く力」が鍛えられます。
よく考えた後で正解や解説を確認すると記憶にも残りやすいのでおすすめです!
ただ、知識がないとまるちゃんのようなへりくつ解答になってしまうので気をつけましょうね。