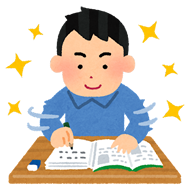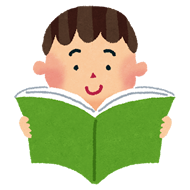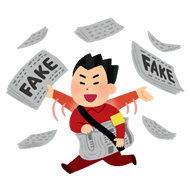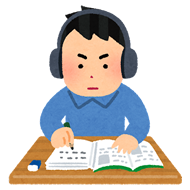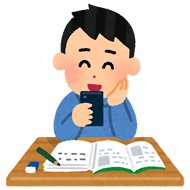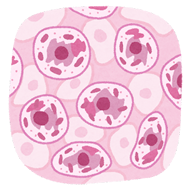プロのスポーツ選手はそのスポーツをすることで報酬(給料)を受けます。高い給料をもらっている選手がいる一方で、一般的なサラリーマンよりも低い給料しかもらえない選手もいます。その差は何なのでしょうか。当然プロなので能力が高くなければ活躍できませんが、能力が高くても評価されない選手はたくさんいます。人の価値は「どれだけ多くの人から必要とされているか」で決まると考えます。
何もかも一生懸命なA選手がいるとします。練習時は物凄い量の練習をし、試合時は敗戦寸前でもあきらめず、勝とうとする姿勢を崩しません。後輩は「あの先輩があれだけ練習するのだから、自分も負けずに練習しよう!」と思う。そんな風に思う選手がたくさん出てくれば、間違いなくそのチームは強くなるでしょう。また観客は「全力でやっている選手のために大きな声で応援しよう!また試合を見に行って応援しよう!」と思う。そうするとチームの関連会社の売り上げが上がります。A選手はチームからもファンからも必要とされていてそのチームには欠かせない存在であるため、給料は必然的に上がっていきます。そしてその結果A選手はこう思うにちがいありません。「もっと結果を出して、ファンを喜ばせたい!より一層頑張るぞ。」
もうすぐ新しい学年になりますね。あらためて、まずは与えられた課題をしっかりこなしましょう。やりきることで学力はもちろん、忍耐力や集中力、苦手から逃げない心など社会に出てからより求められる人間力が高まります。2022年度も頑張っていきましょう。