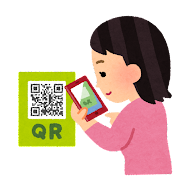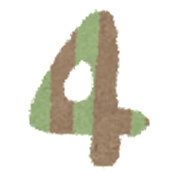最近の映画にも登場する『伊能忠敬』。時刻表を見ることと地図を見ることが好きな私にとって興味深いですが、まだ映画は見ていません。
伊能忠敬ってどんな人?初めて日本地図を作った人、こつこつ歩いて測量を続けた努力家、50歳を超えて自分の夢を実現した人ってイメージです。
伊能忠敬の目標は、「この地球の、正確な大きさを知りたい」
という壮大な野望から50歳の時に19歳年下の高橋至時(よしとき)に弟子入りして天文学を学んだそうです。当初、忠敬は江戸の自宅と勤務先の距離を測って地球の大きさを算出しようとしました。すると師匠の高橋が「そんな短い距離では誤差が出るに決まっている。本気で計算したいなら江戸から蝦夷地(北海道)くらいの距離を測らないとでてこない。」と叱られたそうです。そして当時、通行手形がないとあちこちにいけない時代に、諸外国から蝦夷地を守りたいと幕府に掛け合いました。蝦夷地を測量して正確な地図を作るべきだと訴え、測量許可をもらって地図は大成功。
肝心の「地球の大きさ」は?忠敬は、緯度1度の距離を28.2里(約110.7km)と算出。現在の最新科学でも、緯度1度の長さは約110.996 km。忠敬の算出した数字は、わずか誤差0.2%で驚くほかありません。地球の大きさが知りたい「目的」のための「手段」が測量と地図作りだったわけです。
地図を作ることが目的ではなかったんですね。
EXオープンや全国統一小学生・中学生・高校生テスト、学校の定期考査の結果が返ってくる時期ですね。たくさんの数字や自分の弱点とも向き合います。
こういう時こそ、目の前にある目標(みんなにとっては受験とか大会など…)の向こう側の自分をおもいっきり思い描いてほしいです。白紙の未来に何を描いてもいいんです。
今、本気で取り組もうとしている目の前のことが、今は全然関係ないと思っていることが、未来の自分に、さらには未来の地球につながっているかもです。