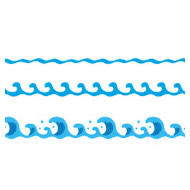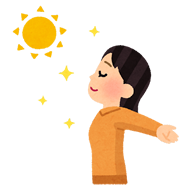
朝晩は肌寒くなり、冬への移り変わりを感じる季節となりました。朝の寒さを感じたと思ったら、昼になるといつの間にか心地よい気温になっていることに気が付きます。秋の季語に「小春日和」という言葉があります。辞書で調べると、『11月から12月にかけての,よくはれた春のような感じがする,あたたかいひより。』とあります。春先のことだと勘違いをしている人が多い言葉でもありますね。
明治期の作家、島崎藤村が『秋から冬に成る頃の小春日和は,この地方での最も忘れ難い,最も心地の好い時の一つである。』と随筆の中で書いています。ただ「寒いなぁ」とか「暑いなぁ」とか日頃から簡単に言ってしまっていますが、この変化を感じることができる人は、いろんなことを楽しめる人だと思います。
皆さんは季節の変化を感じて、この学年で達成したい自分の目標に向けて努力しているところだと思います。特に受験生は、入試本番に向かっていきます。受験生は、目の前の一問一問に全力をかけて、秋のあたたかさを感じる余裕がないかもしれません。ふと窓の外を見ると紅葉している木々があり、夕方になるとコートを着ている人がいます。
あっという間に冬になる季節、気温の変化に体調を崩さず、変化を楽しみながら、入試までの限られた期間を計画的に学習していきましょう。