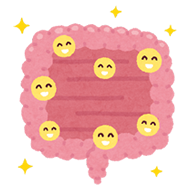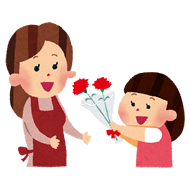勉強をしているとどうしてもついて回るものが点数、成績、偏差値、順位…。
冷静に考えると本当に大切なのはそんなことではない。
みんなわかっているけれど、頑張っているかどうかの判断基準に使いがちだから、気にしないわけにはいかない。
テストで悪い点を取ってしまったり、偏差値が低かったりすると落ち込みますね。「自分はダメなのかもしれない…」と。
そんな時、少し考えてほしいのです。
自分がどれくらい勉強ができるかは自分が一番よくわかっています。
クラスの中でどのくらいの順位かを想像してみよう。
1位はあの子で、2位はあいつで…という感じで。
そうすると集団の中で自分の位置が見えてくる。
そうやって考えた順位が、いわゆる「偏差値順」なのです。
そして、一つ自分に質問してみよう。
20年後に、ここにいる全員が再会したら、この偏差値順の通りに幸せになっているかどうか…、やはり順番通りに1位の人が一番お金持ちになっているのか…。
答えは必ずしもそうではありません。
偏差値順というのは、将来の何かを保証する順位ではないのです。
では、「偏差値順」とは何の順?
それは、「今まで勉強を楽しんだ順」と言えるかもしれません。
そして楽しむとは、一生懸命に英単語を覚えたり、自分から進んで勉強した内容をノートにまとめたりすること。
その頑張った結果として、知識が増えたり、解けなかった問題が解けるようになることです。
間違えてはいけません。
偏差値は勉強した時間の長さに比例するわけではありません。
嫌々やったり、面倒だなって思いながらやったり、苦しみながらやっても偏差値は上がりません。
楽しんだ順だから。もちろん成績も同じです。
どうせやるなら、成績も偏差値もぐんぐん上がるやり方でやった方が良い。方法はただ一つ。
「勉強を楽しむ!」
この夏、講習会や合宿を通して勉強を楽しみましょう!