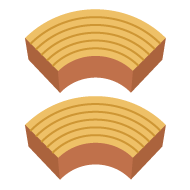 誰もが知っている推理漫画『名探偵コナン』。
誰もが知っている推理漫画『名探偵コナン』。
初登場から四半世紀近くの歳月が流れた今でも絶大な支持を得ながら、現在、コミックスは93巻まで刊行され、テレビアニメは22年目を迎えています。
また、劇場版アニメも年1本のペースで計21作公開され、ここ最近では4年連続で最高興行収入を更新し続けるなど、国民的作品として、ますます上昇傾向の人気を誇っています。
大人顔負けの抜群の頭脳を持つ高校生探偵・工藤新一。彼は、黒尽くめの男たちによって試作段階の毒薬を飲まされ、身体が縮んで幼児化してしまいます。
自分が生きていることを知られたら再び命を狙われて周囲の人間も巻き添えにされてしまうため、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、黒の組織の行方を追いながら、持ち前の推理力と洞察力、更には万能アイテムを駆使して、次々に起きる警察もお手上げの難事件を解決していく。そんなストーリーなのですが、アニメ版第652~655話「毒と幻のデザイン」では、目の錯覚を利用したいくつかの幾何学的なトリックを使ったある事件が発生しました。
その中の1つは「ジャストロー錯視」。心理学者のジャストローが100年以上前に発見した、まったく同じ大きさのカマボコのような扇型の図形を並べると、扇の中心の側に置いたものが大きく見えるという誤認識で、本編では、大きく見えるバウムクーヘンの方に毒が降り掛けられていました。
ミュラー・リヤー錯視やツェルナー錯視など、形の錯視だけでも実に多くの種類が存在します。加えて、明るさや色の錯視もあり、一度調べてみると面白いですよ。
もう1つは「ゲシュタルト崩壊」。ゲシュタルトとは、ドイツ語で「形態・姿」というまとまりのある構造を意味します。
本編では「若」という漢字が使われていましたが、一つの漢字を長時間注視することにより、その漢字の各部分がバラバラに見え始め、よく知ったものでも、その漢字が何という文字だったかわからなくなってきます。
すなわち、姿かたちが壊れて全体性が失われてしまい、個々の構造部分に切り離して認識し直してしまう知覚現象なのですが、漢字ドリルでの練習などで、何度も同じ漢字を書き続けたときに、こんな感覚になったことはありませんか。(夏目漱石の小説「門」の冒頭近くでも、この現象に関連する場面が出てきます。)
例えば、「借」「貯」「弾」「秋」「粉」など、別々に意味を持った文字で構成される漢字は特に崩壊しやすいようです。(解・話・勇・校・較・明…、挙げればきりがありません。)
黒の組織の陰謀によって数々の苦境にさらされ続けてきたコナンですが、今回の事件に限らず、彼はいつも、正義の心と勇気を持って、謎に立ち向かっていきます。
そして、真実を解き明かすためには、どんな状況になっても諦めるということをしません。自分の大切な人たちが危機にさらされたとき、どうすれば助けることができるのか、どうすることが最善なのか、どうすれば居場所を特定できるのか、という風に、「どうすれば今の目的が達成できるか?」ということだけを考えています。つまり、コナンの生き方は、常に、「何でできないのか?」ではなく、「どうすればできるのか?」というポジティブな考えがベースになっています。
人は、否定的な問いかけを自分にすると、自己暗示が進行してどんどん自分に自信がなくなり、失敗を恐れ、何もできなくなってしまいます。逆に、肯定的な問いかけができるようになると、ふとしたときに解決策が浮かんできたりします。この「どうすればできるのか?」という問いかけには、これから達成しようとする目的に対して、「自分ができない」というネガティブな要素がありません。
だから、自分に対するマイナスイメージも軽減されます。問いかけ一つを変えるだけで、何か問題(壁)にぶつかったときの行動も、まったく別のものに変わるのです。
暑くて長い夏休み、頑張ろうとしている勉強のたいへんさにめげそうになったとき、コナンの前向きな思考をぜひ思い出してくださいね。
 「怖いリンゴの絵を書いてください」と言われるとみなさんはどんな絵を書きますか。
「怖いリンゴの絵を書いてください」と言われるとみなさんはどんな絵を書きますか。
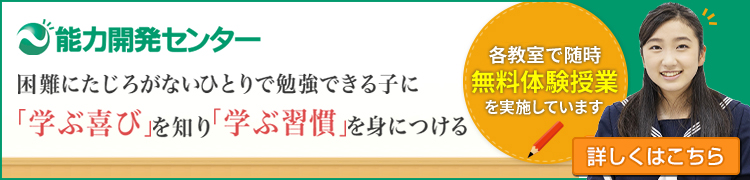
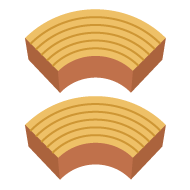 誰もが知っている推理漫画『名探偵コナン』。
誰もが知っている推理漫画『名探偵コナン』。 プールサイダーという言葉があります。プールで飲むサイダーじゃないよ。念のため。
プールサイダーという言葉があります。プールで飲むサイダーじゃないよ。念のため。 これは有名構文を使った英文で、小中学生の皆さんにはちょっと難しいかもしれませんが、「カーナビと道路地図の関係は、先生と参考書の関係と同じだ」という意味です。何を言いたいか、今から説明します。
これは有名構文を使った英文で、小中学生の皆さんにはちょっと難しいかもしれませんが、「カーナビと道路地図の関係は、先生と参考書の関係と同じだ」という意味です。何を言いたいか、今から説明します。  15年ほど能開の先生をやってきました。
15年ほど能開の先生をやってきました。