
春は、新しいことが始まる季節ですね。
新学年になって新しい目標を立てて、今から頑張ろうとしている人も多いでしょう。
そんな目標を決めて頑張るために必要なことが最近読んだ「ワールドトリガー」に書いてありました。
知っている人も多いと思いますがSQジャンプで連載中のマンガです。
日本に突然現れた異世界の怪物「ネイバー」とそれに対抗する民間の組織「ボーダー」の戦いを描いたSFアクションマンガです。
最新28巻では、異世界へ遠征に向かうチームを選抜する試験が描かれています。
その試験はチームで課題に取り組むのですが、あるチームでリーダーに選ばれた麓郎(ろくろう)が自分の実力に疑問を抱きチームメイトに助言を求める場面があります。
チームメイトから彼に向けられた言葉の中にこんな言葉がありました。
「目標に期限がない場合、失敗を正しく認識できないことがある。」
その他にもなんだか難しいことを言っていましたが、要するに、目標達成の期限を切らないとその目標が達成できたかどうかの判定を無限に先送りすることができてしまう。
期限がないと、いつまでも「まだ挑戦中です。だってまだ結果出てないから…。」と失敗を認められない。
つまり、いつまでも結果と向き合えないってことですね。
失敗だと分からないうちは現実的な反省や改善ができないから、当然目標達成には至らない・・・
この先送りにしている状態を作品中では「足踏み」と言っています。
さあ、みんなはどうでしょうか。
目標を決めるときに期限を決めていますか?
受験生は、目標への期限は決められていますね。
受験学年でない人もいつかは受験学年になります。
その時のために、今から小さな目標でもしっかりと期限を決めて成功体験を積み上げていきましょう。





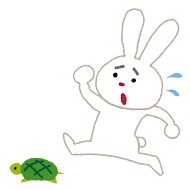
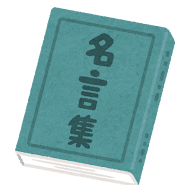



 先生が子供のころ、お父さんから月の土地をプレゼントとして貰ったことがあります。
先生が子供のころ、お父さんから月の土地をプレゼントとして貰ったことがあります。